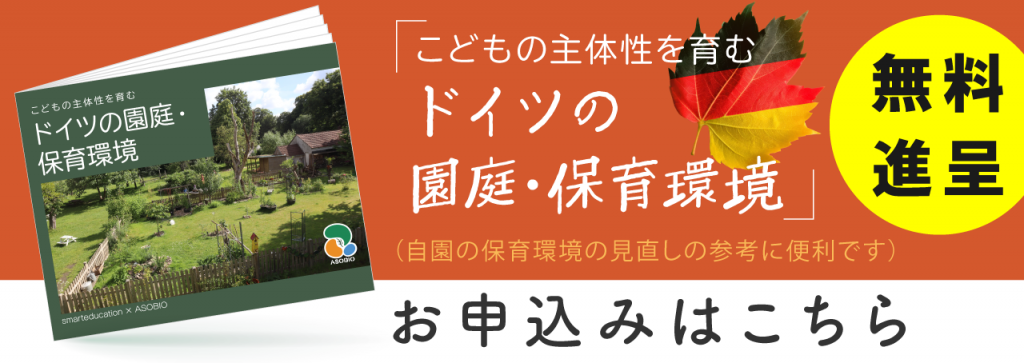ASOBIO・クラスバセミナーレポート 『こども主体の遊びが生れる最新の屋内環境・園庭環境』
3月27日に開催したASOBIO園庭セミナーASOBIO・クラスバセミナーレポート 『こども主体の遊びが生れる最新の屋内環境・園庭環境』のセミナー動画の見逃し配信(アーカイブ)や、質問と回答をご紹介します。
セミナーの開催概要はこちらです。
セミナー動画(アーカイブ:90分)
アンケート回答いただいた方に、登壇者3名の資料をプレゼントします。アンケート回答はこちらからお願いします。
セミナー中に頂いた質問と回答
Q:子どもの姿から理想の環境を作ると、どうしても死角が増えてしまいます。午睡スペースが保育室のため、監査の時に死角が多いと指摘されました。どうしたら良いのでしょうか。(たまがわみんなの家さん)
Q:園庭も同じで死角が増えると安全面での不安が職員にも保護者にも生じると予想しています。どのように理解を深めていったのか知りたいです。(あゆみらい保育園さん)
A:死角に関する質問なので、まとめて回答をします。危険を回避する前提で死角は大きなリスクがあるのは確かです。しかし、園の生活の中で常に先生の視界の中にこどもがいる事が望ましいのか、考える必要があります。こどもの主体性の観点、こどもの人権の観点を考えると、身を隠したいという気持ちも尊重する必要があるのだと思います。
午睡スペースの確保のために、ホール(空いているスペース)を活用したり、環境を工夫するケースもあります。監査に関しては、環境設定の意図をしっかり説明できる事、監査する側もハード面だけでなく、ソフト(先生の連携)も含めて、監査の質を向上する必要があるのだと思います。
Q:以上児などは、ビー玉や小さな部材での遊びが必要だと思いますが、低年齢児の誤飲などが心配です。(いちご保育園さん)
Q:コーナーを作ろうとしていますが、コーナー間のおもちゃの移動を危ないからと制限したり、玩具の遊び方の制限がおきてしまっています。ある程度のルールを設ける必要はあるのでしょうか。ルールの線引きが難しいと感じてしまいます。(出合保育園さん)
Q:コーナー遊びや死角についての職員の意識や同じイメージの共有がとても難しく感じています。最初の一歩はどうすれば……(ひよこ第3保育園さん)
A:コーナーに関する質問なので、まとめて回答をします。まず始めに年齢に合わせた保育環境を作る必要があります。3歳以上と未満時のスペースを物理的に部屋で分ける等、工夫が必要です。はさみ等の危険が伴う道具は置く場所、使う場所の制限も大切です。ルールを作る事は悪い事ではありませんが、ルールありきになると先生の思考が停止し、逆に事故につながることもあります。こどもの興味関心にしっかり注目し、先生が語り合い、ルールを含めた環境を再構築する風土が大切です。
Q:室内、屋外環境を含めてですが、今後の小学校教育に関して、先ほどの小学校低学年のコーナー事例などもそうですが、特に低学年に関しては、室内室外環境などは幼児教育の延長線上のような環境や遊びのブームなどの活動に小学校も変化していくとうれしいなと思いますがどうでしょうか?(めぐみこども園さん)
A:学習指導要領の改訂の議論の中で、小学校の低学年は、幼児教育で重視しているか「環境を通じた保育(教育)」を取り入れる議論がされています。横浜市の小学校では具体的に低学年の教室にコーナーが配置され、成果が確認されています。不登校のこどもが増える中で、小学校教育にもこども主体の学び(個別最適な学び)の流れが確実に生まれています。公開保育で地域の小学校の先生をお呼びしたり、先生同士の対話がとても大切になっています。
Q:ICTの面白い使い方や事例があれば沢山教えて欲しいです!また、初めは仕方ないかとは思いますが、どうしても目新しいものに子どもの興味が集中してしまうことも予想されます。「さりげなく」するためのコツがあれば教えて欲しいです。(手稲やまなみ子ども園さん)
A:ICTを導入する以前に、従来の保育環境でこどもが遊びこめているかを考える事が大切です。ICTは刺激が強い側面もあります。ICTに負けない(使わなくても遊びこめる)環境がまずあって、その遊びを更に広げるためにICTを導入するのが良いと思います。具体的な事例が書籍になりました。
ICTで広がる保育ぜひご覧ください。
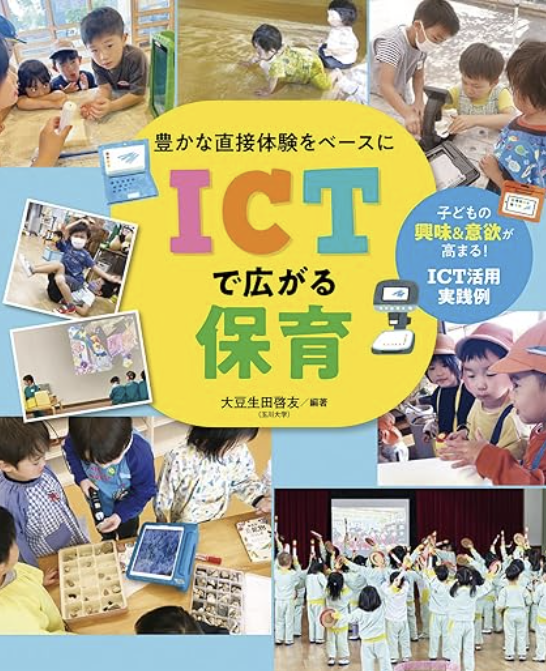
Q:子ども主体の保育の中で屋内、屋外での子どもの所在の把握をどのようにしていますか?(いちご保育園さん)
A:死角の有無に関わらず、こどもの所在を先生が意識する事は必須だと思います。先生の意識がある前提で、先生間の連携を補助するためにIP無線機等を活用する事例もあります。
Q:環境に関しては、本日お話しいただいたような環境作りをしており、子ども主体のあそびを進めていますが、お片付けをいかに子ども主体で行うかという意見が職員間で出ます。何か良いアイディアはないでしょうか。もちろん、片付けについても子どもたちと常に話し合っていますが、なかなかうまくいきません。(天満幼稚園さん)
A:片付けもあそびの1つ(一連の流れ)として伝えていく必要があるのだと思います。こどもの興味関心が他コーナーに移り、散らかったまま放置されたコーナーを見かける事はあります。自分やお友達が気持ち良くコーナーやその中のツールを使うためには、どうすればよいのか、こどもに問いかける必要があります。生活の中で、社会性や道徳心を育む良い機会だと考えてはいかがでしょうか。