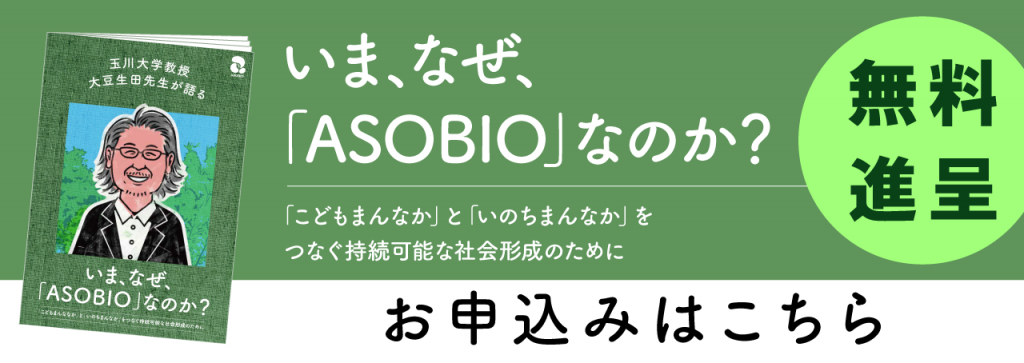雨庭と自然豊かな園庭づくりシンポジウム ~質問と回答~
2025年6月28日(土)の熊本県立大学で開催された、雨庭と自然豊かな園庭づくりシンポジウム2025のパネルディスカッションの質問と回答です。会場で回答できなかった、すべての質問と回答です。
開催概要はこちらをご覧ください。
パネルディスカッションにて回答済みの質問
Q1: 園庭の植えるおすすめの植物はありますか?相性のよい組み合わせなどお聞きしたいです。(この植物があれば蚊がこない、これとこれを植えると育ちやすい、この植物を植えるとこの虫を呼び寄せられるなど)
A:地域によっても植生は異なるので、これという回答は難しいです。「実を食べたい」、「どんぐりであそびたい」「色水あそびをしたい」、「虫が集まるようにしたい」等、先生がこどもとどんな遊びをしたいのか考えてみてください。それを元に、インターネットで検索をしたり、私たちスマートエデュケーションにご相談ください。また、園芸店に足を運び素敵だなと感じた植物を植えてみてもよいと思います。ハーブ等は虫よけの効果はありますが、蚊が来なくなる事はありません。Q2の回答も参考にしてください。
Q2:雨庭、ビオトープによる蚊の発生の状況はどうなのでしょうか。自然の姿と捉えるべき?虫刺されが気になるご家庭も多いので、状況をお伺いしたいです。
蚊は水場で産卵し、やがて成虫になります。ビオトープ等の水場にはメダカやフナ等の地域の魚を飼育すると効果的です(水と生き物の循環環境を作る事が大切です)。ただし、蚊は植物にとまる事が多いので、ゼロにする事は難しく、自然の姿と捉える必要があるのかもしれません。適度に剪定を行い、風通しのよい環境を維持する事や、園児がいる時間は蚊取り線香を使うのも効果的です。
自然を取り入れる事は、一定のリスクは伴います。職員や保護者との対話、理解がなにより大切です。持続可能な社会の実現のために、蚊に刺される経験も必要なのかもしれません。
Q3:雨庭や水の流れるビオトープを作ってみたいと思いますが、今、現在でも蚊の発生が多く、溜まり水にボウフラができることはないのでしょうか?
A:Q2と同じ回答です。溜まり水を放置すれば、ボウフラ(蚊の幼虫)が発生します。水や生き物が循環する環境を作りましょう。
Q4:園庭が斜めになっており、1番下に排水溝があるため雨のたびに水捌けはよいが砂がながれてしまうので困っている。定期的に砂を入れているが、砂を流さない為にも、雨庭を検討中です。海が近いことと、台風による被害が多い地域ということもあるので、どんな木を植えたらよいか、また、うちの園にピッタリな雨庭のアドバイスをお願いします。
A:土留めのために、植栽をされるとよいと思います。水捌けの良い土壌は植栽には適さないので、土壌の改良も必要です。私たちスマートエデュケーションにご相談ください。
Q5:雨庭を作る為の予算について、補助金などがありますか?
A:補助金は各地の自治体にご相談ください。
Q6:ASOBIO がとても素敵でしたが、導入にあたっては予算がないと難しいと感じました。費用感や活用できる補助制度などあれば教えてください。
A:広さ、土壌の状態により費用に幅があります。ご予算に合わせて研修、施工する場合が多いです。地域によっては補助金が使える場合もあります。私たちスマートエデュケーションにご相談ください。
Q7:肥後銀行さんに質問です。取り組まれている内容が単なる企業のCSRにとどまらない、地域全体を巻き込んだもののように感じます。かなり投資もしているようですが、その目的や、問題意識を持ったきっかけなどがあれば教えていただきたいです。
A:当行は、熊本県を地盤とする地域銀行として存在しており、県内事業者の約6割が当行をメイン銀行としてお取引いただいております。また、熊本県をはじめとした多くの県内自治体様の指定管理者として、会計面だけでなく様々な地域課題にも永年率先して関わらせていただいております。
当行は、企業理念と同列で「私達の存在意義〔パーパス〕」を公表しておりますのでご紹介します。
「私達は、お客様や地域の皆様とともに、お客様の資産や事業、地域の産業や自然・文化を育て、守り、引き継ぐことで、地域の未来を創造していく為に存在しています」
熊本は水の国ともいわれますが、当行は源流の阿蘇地域において永年植樹活動や耕作放棄地の水田再生に取り組んでおり、まさにパーパスを実践している次第です。
今後とも「その地域にどんな地方銀行があるかによって、その地方の未来は変わる!」の信念のもと、地域に寄り添った活動を行ってまいります。
Q8:初心者でも簡単に園庭に雨庭を作る方法を教えて下さい。
A:雨水を下水や側溝に流さずに、園庭に流れる工夫をしてみる等、様々な方法があります。くまもと雨庭パートナーシップやスマートエデュケーションにご相談ください。
Q9:泥遊びをする中でどうしても保護者の洗濯物の負担が課題になります。洗濯で落ちやすい泥、洗うと落ちやすい繊維でできた衣類など、おすすめはありますか?
A:汚れが落ちやすい繊維でできた運動服はあります。ただし、こういった心配は保護者の保育への理解、信頼関係に起因する場合が多くあります。自然を取り入れる事は、一定のリスクは伴います。職員や保護者との対話、理解がなにより大切です。
理解をいただくために、保育ドキュメンテーション(日常の保育を写真や動画、コメントで共有する手段)も効果的です。「泥だけを家に持ち帰らない」ように、日常の成長の姿を共有する事も大切です。
Q10:園庭にビオトープを形成するなかで同じ植物が茂ってしまい、他の植物が負けてしまう場合(ドクダミなど)、それも「自然」とするべきか、ある程度駆除して整備する方がいいのか迷います。ご意見をお伺いしたいです。
A:園庭ビオトープは自然再生のために作られる一般的なビオトープとは異なり、自然を経験するための教育・保育の場です。よって、こどもの多様な経験のために、植物を管理、剪定、整備する事も大切です。ドクダミやクローバー、ハーブ類は繁殖力が強い植物です。整備は問題ありません。ただし、ドクダミ=悪者ではありません。ドクダミ茶になったり、立派な在来種です。ドクダミにも命がある事をご理解ください。
Q11:ASOBIO様など発表者の皆様のスライド資料を共有していただくことはできますでしょうか?(案内を聞き逃していたら申し訳ございません。)
A :アンケートに回答いただいた方に共有をします。ご意見ありがとうございます。
Q12:園長ですが、今日は個人的に参加しています。この感動を職員と共有したいのですが一緒に学べる機会がありますか?
A :ありがとうございます。アンケートに回答いただいた方に本日の録画、資料も共有します。園で研修も可能です。わたしたち、スマートエデュケーションにご相談ください。
Q13:時代によって幼児教育も流行りがあるように感じます。現在の環境も今の最善だとしたら、社会の変化が加わった20年後の園庭はどのような園庭になっていると予想しますか?
A:SDGsやESD、グリーンインフラの思想は、100年以上前の産業革命以降の地球規模の環境破壊に起因し、世界で共有されている課題であり、長い歴史の中で必然的に発生した取り組みです。雨庭やASOBIOといった各種取り組みは新陳代謝すると思いますが、20年後も本質的な課題は残り続けるのだと思います。
未回答の質問への回答
Q14:自然豊かな園庭づくりの事例紹介がありましたが、一つの施工事例で差はあると思いますが、大体どのくらいの予算でできるのでしょうか?
A:Q6と同じ回答です。
Q15:過去の事例に園庭の環境について大きな事故などありましたか?意外と気づかない手作り遊具の誤った設置の仕方、毒植物による事故など、園庭において危機管理を園庭のプロの視点からお聞きしたいです。
A:私たちが施工した園庭で大きな事故はありません。手作り遊具に関わらず、事故は耳にします。一番大切な事は、園庭環境作りに職員(担任の先生)が加わっているか、あそびの姿の振り返りが行われているか、放置になっていないかという事です。危機管理は、ノウハウやルールだけでなく、管理者と職員が同じ目線でリスクやハザードを対話し、危機管理意識を共有する事が大切です。
Q16:幼稚園の園長です。自分で自分なりに雨庭を造りましたが、狭いタイプですが費用がかなりかかりました。予算捻出の厳しさを感じています。いいアイデアがありましたら教えてください
A:くまもと雨庭パートナーシップやスマートエデュケーションにご相談ください。
Q17:ビオトープを人為的に作ることは意外と難しく、子どもと大人が一緒に考えて作るということが目から鱗というか面白いあり方だと感じました。子どもたちが危険な生物を見分けるためには先生方がまず理解しておかないと説明できないと思うのですが、どうやって学ぶとよいのでしょうか
A:自然の生物には毒や危険があるのは事実ですが、神経質になりすぎるのはよくありません。結論から言えば、日常生活で触れ合う中で大きな危険は発生しません。不安もあると思うので、専門家に相談をおすすめします。日本生態系協会やスマートエデュケーションにご相談ください。
Q18:今の園庭は昔ながらの運動場です。硬いです。掘ったり、木や植物を植えることができなくて、植木鉢対応でどうにか緑を増やしています。三分の一の広さでも土壌改良ができたらと思いますが、そういう時はどういう業者に依頼するのでしょうか?
A:スマートエデュケーションにご相談ください。造成業者さんや造園屋さんに依頼をしますが、園庭環境に適した施工ができる会社が少ないのが事実です。ご紹介します。
Q19:他県からの参加ですが、熊本県さんのように官民連携で雨庭を推進するには様々な努力ご苦労があったかと思います。このような動きにつながったキーパーソンがいらしたのか、秘訣など参考にさせていただきたいです。
A:Q7でも回答しましたが、熊本で自然災害が重なったこと、流域治水の専門家である島谷先生の存在は大きいと思います。シンポジウム内でも紹介しましたが、グリーンインフラや流域治水や雨庭の考えは全国に広がっていきます。
Q20:雨庭の衛生面について 留意点を教えてください
A:溜まった水が3日以内に浸透する事が1つの目安です。ビオトープタイプであれば、水が循環する環境(自然排水できなければ、ポンプをつけ水を循環させる)や、生き物を飼育する事が大切です。
Q21:肥後銀行様 貴重なお話ありがとうございました。雨庭を通じて、多様なステークホルダーと協力する中で、共創図る指標がありましたら教えてください
A:令和2年7月豪雨を契機として熊本県立大学、熊本県、肥後銀行の産官学が幹事機関となった10年間の「共創の流域治水プロジェクト」が国の支援のもと開始されております。解決策の柱として、従来のダムなどのコンクリートに頼った治水対策ではなく、田んぼダムの普及や雨庭の設置、森林管理など流域全体で、水を管理する技術の研究と普及活動を開始しているところです。
「雨庭」を普及するうえで掲げたスローガン〔共創図る指標〕が、「プロジェクトの最終年である2030年までに2030個の雨庭を熊本県内につくろう」です。2023年5月には、当行大ホールにおいて、このスローガンに共鳴いただいた自治体、企業、教育機関など多くの方にご参加いただき、任意団体「雨庭パートナーシップ」を立ち上げました。
また、最近では大量の水を取水する半導体工場の進出に伴い、水の保全対策としての「雨庭」も効果的であることが研究で分かってきたことから、半導体関連企業からの問い合わせも多く、今後「雨庭」の設置普及が加速化すると見込まれております。
Q22:ASOBIOの概念は、今後、公園や小学校等に展開する可能性はありますでしょうか。幼児までの間で自然と触れ合う体験が途切れてしまうのはもったいないと思いましたので。
A:今でも公共施設での設置の相談をいただいています。幅広い普及を考えてまいります。ありがとうございます。
Q23:南稜高校の雨庭事例で、浸透する水量が造成前より減少したグラフがありましたが、元々の土地の状態によって雨庭を造るかどうかは、用いる素材や施工方法含めて専門家等に相談して慎重に検討した方がよろしいものでしょうか。
A:園であれば、試行錯誤する事も大切だと思います。南稜高校の事例でも一連の試行錯誤が結果的に生徒の探究活動に繋がっている事がわかります。専門家に相談しながら、先生や園児を巻き込みながら作ってはいかがでしょうか。雨庭に関しては、くまもと雨庭パートナーシップやスマートエデュケーションにご相談ください。
Q24:雨水の貯水タンクを手作りして園庭の砂場遊びなどに使っている園を見たことがあります。こうした取組も「雨庭」の1つとして捉えられるでしょうか?
A:雨水を土壌に浸透させる過程で植栽をする等、生物多様性をケアしながら浸透させる工夫が必要です。
Q25:雑草を生やすことに今力を入れているのですが、真夏に種を蒔いたりするのは有効ですか?
A:有効です。クローバー(色々な種類があります)は良い緑肥になります。水やりも大切です。
Q26:保育園でビオトープを整備する際に予算以外で一番のネックとなるのは何でしょうか?
A:先生や職員との対話を通した理解です。Q2やQ9を参考にしてください。
Q27:雨庭と、食育のための菜園は別ですか?
A:菜園に使う水に雨水を使い(雨水パイプの水をタンクにためて使う等)、土壌に浸透するしかけがあれば雨庭にできる可能性があります。
Q28:園庭に、遮光ネットを張り巡らしていますが、昨今の気象状況と自然と共生していけますか?
A:昨今の気象状況(酷暑)で、自然環境を園庭に作る事は工夫が必要です。工夫をすれば実現は可能です。スマートエデュケーションにご相談ください。
Q29:島谷先生 貴重なお話ありがとうございました。2030年までに2030箇所熊本県内で増やすにはどのような方法を考えていらっしゃいますか?
A:2023年にくまもと雨庭パートナーシップを立ち上げ、雨庭の認定や表彰、整備に関する相談などを行いながら、雨庭の認知度の向上と整備の広がりを推進しています。また、2025年3月には、熊本の地下水保全に向けて、グリーンインフラの導入による水循環保全を推進する「熊本ウォーターポジティブ・アクション」が始動しました。今後はこの取り組みとも連携しながら、雨庭のさらなる広がりを目指しています。
「2030年までに2030箇所の雨庭を」という目標は、「30by30」の概念に着想を得て掲げられたチャレンジングな数値目標です。「熊本ウォーターポジティブ・アクション」との連動により、雨庭の普及が加速することが期待される一方で、実現には多くの努力と協力が必要だと認識しています。
※ 30by30…2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」2030年グローバルターゲットの1つです。
Q30:SDGsミライパークは誰でも入れるのでしょうか?子どもを連れて行っても楽しめますか?
A:どなたでも可能です。ワークショップもあり、お子様でもお楽しみいただけます。
https://www.kumamoto-airport.co.jp/study/kumamotomiraipark
Q31:雨庭や自然豊かな園庭をみたり、講演を聴いたりして羨ましいかぎりです。そういう環境がある施設ですぐにでも働きたい思いでした。経営者ではないのでこの良さを伝えるのは難しいし、改革の費用が莫大になることがネックで現実には難しいかなあと夢に終わってしまいそうです😣
A:園の先生でしょうか。回答ありがとうございます。仲間と共有して、理事長先生や園長先生に相談してはいかがでしょうか。伝えづらければ、スマートエデュケーションにご相談ください。お手伝いします。持続可能な社会の実現は1人1人の小さな行動が大切です。
Q32:雪が積もる地域の環境構成などお聞きしたいです。雪が積もる事を仮定したうえでこのような環境を整えているなど工夫をしている事例はありますか?
A:北海道でも実現した実績があります。スマートエデュケーションにご相談ください。
北海道別海町 別海くるみ幼稚園のASOBIO
Q33:池谷社長の話が分かりやすかった。子育ての実体験をもとに教育保育の変革の起点への原点、これからの教育保育のベクトルを共有してもらえた点。感謝!
A:ありがとうございます。これからも頑張ります。
Q34:修士論文にて、雨庭の調査をしようと思っている者です。そこで、雨庭に植える植栽としてはどのような植物を植えた方が良いのか伺いたいです。
A:Q1と同じ回答です。雨庭に関してはくまもと雨庭パートナーシップにお問い合わせください。
Q35:雨庭は雨が降ったときは水が溜まりますが、それ以外は水が溜まってない状態になるのでしょうか?雨庭でメダカなどの魚を取り入れるにはどうしたらいいのでしょうか?
A:熊本県立大学に設置された雨庭は、雨が降った数日後には水が土壌に浸透し、水はなくなります。雨庭は、熊本県立大学に設置されたタイプだけでなく、様々な形状があります。雨水パイプを水のビオトープ(メダカ等を飼育する)に入れる形状もよいと思います。スマートエデュケーションかくまもと雨庭パートナーシップにご相談ください。
Q36:先生主導ではなく、子供が探求する教育の形が印象的でしたし、最近のトレンドでもあります。教育に携わる池谷様は、日本でも注目され始めたホームスクーリング、フリースクールについてどう思われますか?
A:教育場の選択肢が増える(こどもが選択できる)という意味でとても有効だと思います。広がっていく事を祈っています。
Q37:緑を多く植樹することで排気ガスなどの汚染を軽減することはできますか
A:排気ガスに含まれる温室効果ガス(二酸化炭素)は植物の光合成により酸素に転換されます。よって汚染の一部の軽減につながるといえます。
Q38:既成の滑り台にお金をかけるより、雨庭がいいなと思いますが、予算が気になります
A:その通りですね。園庭=グランド&遊具の時代から変化し始めています。予算に関してはQ6と同じ回答です。スマートエデュケーションにご相談ください。
Q39:熊本ウォーターポジティブアクションに絡めた雨庭作りについて興味があります。具体的なアイディアがあれば教えてください
A:くまもと雨庭パートナーシップのホームページを参照したり、お問い合わせください。
Q40:池谷さんが言われた熊本の造園業者さんはどちらですか?
A:造園業の会社、個人は複数人いらっしゃいます。スマートエデュケーションにご相談ください。
Q41:園でのリスクに対応する能力を育むことは、個人や社会が災害に対処するために重要だと感じました。今日のパネルは面白かったです。ありがとうございました。
A:ありがとうございます。持続可能な社会の実現のために、こどもたちと一緒に考えていきましょう。
Q42:園庭に築山がありますが、芝が根付かず土砂崩れがよく起こります。築山には姫りんご、グミの木、紅葉などの木も植えていますが、根っこが剥き出しになって危険な箇所もいくつかあります。土砂崩れが起こらない良い方法があれば教えてください。
A:土壌の改良が上手くできていなかったり、レイアウトに工夫をすれば改善する可能性があります。スマートエデュケーションまでお問い合わせください。