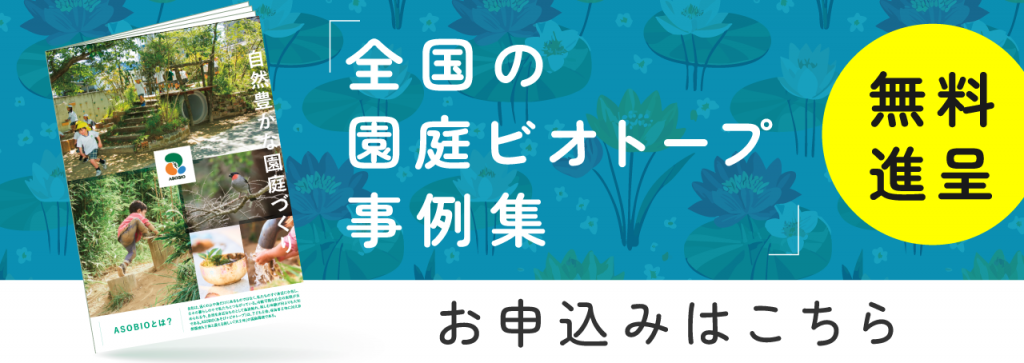園庭ビオトープの作り方~手軽なビオトープの作り方を分かりやすく解説~
園庭にビオトープを作りたい。そんな先生が増えています。こども主体の保育が広がるにつれて、こどもの興味関心を広げたり、自然を身近に感じてほしいとの想いから、園庭にビオトープを作る園が増えています。でも、「どうやって作ったらよいの?」「自分たちでもできるのかな?」そう感じる先生も多いはずです。このコラムでは、自分たちでも手軽に作れるビオトープから、本格的な水場のあるビオトープの作り方をご紹介します。
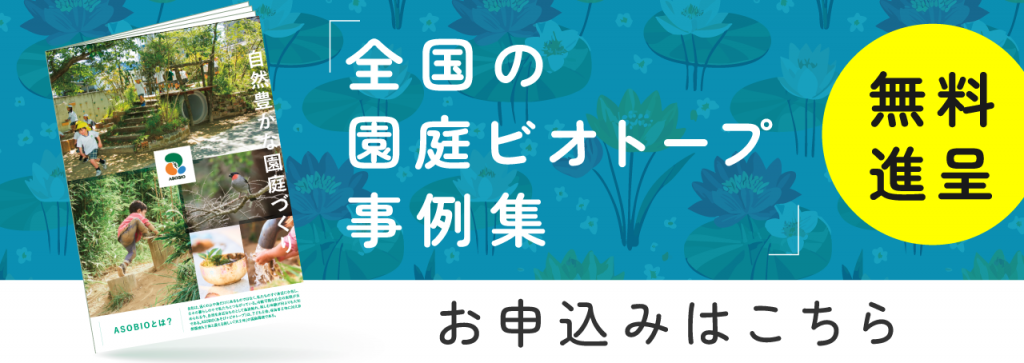
理想の園庭とは
こどもや先生にとって、理想的な園庭とはどんな園庭でしょうか?私たちは園庭を考えるうえで「多様に身体を動かす場」「想像や創作を広げる場」「自然との関わりを持つ場」という3つの場を大切にしています。

その3つの場と身を隠す場や静かに過ごす場、園舎と園庭をスムーズに往来できる中間領域などの動線や景観も含めてバランスよくデザインしています。また、園庭に自然を誘致するポイントは「地域性」です。地域に合った土や植物を選ぶことで虫や鳥が集い、やがて在来種を中心とした生態系を創ることに繋がります。
園庭が子ども、先生、保護者だけではなく、地域の人も集うランドマークになることを目指しています。自然に完成がないように園庭に完成はありません。10年後、50年後の姿をイメージしながら計画していくことと、園庭が変化し続ける可塑性の高い環境を目指し、アイデアをすべて詰め込まず、将来の発展に備えることも大切にしています。
ビオトープとは?
ビオトープというと、水場をイメージする方が多いようですが、実は違います。ビオトープのビオ(Bio)は「生きものたち」トープ(Top)は「空間」をさすドイツ語です。 つまりビオトープとは、地域の野生の生きものたちが生息する空間を意味しています。


よって、上の写真の両方がビオトープということになります。海岸の草地や、草原もビオトープですし、園庭の隅っこや、遊具の周りに生えてくる雑草(雑草にも名前はあります)は、そのまま生やしておけば、そこはビオトープという事になります。
手軽なビオトープの作り方
ビオトープの豆知識でお伝えした通り、ビオトープ=水場ではなく、地域の野生の生きものたちが生息する空間ですから、雑草園(草地)を作る事が一番手軽な方法です。1㎡あれば作る事ができる、雑草園ビオトープの作り方をご紹介します。


雑草が生えている場所があれば、そのまま放置して徐々に広げる方法や、園庭の一角にビオトープを作る場所を設けても良いと思います。大切なのは、土づくりです。園庭に使用されている土の多くは、真砂土(まさど・まさつち※)という水はけの良い土です。雨が降った翌日に、運動場として使える(水たまりがなくなる)点では良いのですが、植物の成長には適していません。植物は根っこから水や養分を吸収するので、水はけの良すぎる真砂土はビオトープの土(土壌)には適さないのです。山でハイキングをしたり、畑で作物を作った時の土の色を思い出してください。植物の成長に適した土は、黒土という黒に近い茶色の土です。真砂土はベージュに近い色をしており、土質もサラサラしています。


※真砂土は西日本に広く分布しています。西日本ではビオトープを作る際に、まとまった黒土を入手するのが困難な場合もあります。
簡単にできる土(土壌)づくりの方法
【準備するもの】
- スコップ
- 手袋
- 黒土やたい肥(園芸店やホームセンターで購入できます)
- 園内の草地や周辺の山や河原の土(※)
※園芸店で購入する土には種子は含まれません。園内の草地や周辺の山や河原の土には、種子(地域の植物の種子)が含まれます。
ビオトープを作る場所の土をスコップで耕しましょう。準備した土を混ぜて更に耕してください。耕す意味は、真砂土と入れた土を混ぜる事と、土の中に空気を含ませるためです。植物は土壌から水や養分以外に空気も吸収します。カチカチでスコップが入らない場合には、プロの手を借りる必要があります。ユンボ等の工事機材を使って、同様の作業を行います。
ビオトープの管理の方法



土壌が完成した後は、基本的に放置するか、こどもと一緒に水やりも良いかもしれません。やがて土に含まれる種子が芽を出します。草地になりバッタ等の虫が集まり、そのバッタを捕食するための野鳥がやってきます。野鳥が糞をすると、その中に含まれる種が発芽します。こういった人間が手をかけずに生命が循環する環境ができれば、地域の生き物が次々と集うようになり、そこは立派なビオトープと言えるでしょう。
本格的な水場のあるビオトープの作り方
水場のあるビオトープは、美しく、誰もが憧れる空間です。安定した水場のあるビオトープができれば、メダカやトンボやカエルはもちろん、ゲンゴロウが棲むようになった例もあり、より豊かな自然を楽しむ事ができます。その一方で園庭に水を溜め、循環させる仕組みが必要になります。また、こどもが溺れる事故が絶対にないように安全対策も必要です。プロの手を借りるか、高度なDIYのスキルが必要になります。


水場のあるビオトープの作り方
①設計(計画)をする
園庭のどこに作るのか、計画をします。広さは様々ですが、取水するので、水道や井戸の場所を確認しましょう。
②掘削・造成する

重機を使う場合が一般的です。防水シートやモルタルをうつので、その厚みも考慮して掘削します。
③防水シートを敷設、モルタルで固定・成形、ポンプ、取水経路を作る
循環ポンプ※の場所と取水経路を決めて、防水シートを敷きます。固定するために、モルタルで固定・成形します。私たちが施工する場合、排水(水を抜く)する仕組みは作りません。大雨が降った場合は、オーバーフローする(水があふれる)事を想定し、池の周辺に植栽をします。植栽する事で水の浸透性が上がります。モルタルが固まったら、砂利や土を入れていきます。


※ビオトープに循環ポンプをつける理由は、水のよどみ(滞留)を防ぐためです。また、水が循環する事で水中に空気も取り込まれやすくなるので、メダカ等の生き物が過ごしやすくなります。
④植栽をする
水中も育つ、睡蓮や蓮、水生のトクサを植えたり。水草を入れます。睡蓮等の植栽は、後々のメンテナンスを考えて鉢のまま沈めてもと良いと思います。水草を入れる理由は、景観だけでなく光合成による水中の酸素を増やす事、メダカの産卵床やこどもの隠れ家になります。

⑤(1、2週間し、水質が安定したら)生き物を入れる
近隣の川や田んぼに棲む生き物(フナやドジョウ、タニシ、メダカ等)やを入れてみましょう。フナやメダカは、メダカは、ボウフラ(蚊の幼虫)を好んで食べます。ビオトープ内で産卵もして増やす事ができます。冬も冬眠をするので、水面に氷が張っても、春に元気な顔を見せてくれます。
ビオトープに金魚や、鯉(錦鯉)、アメリカザリガニは入れないようにしましょう。金魚や錦鯉は観賞魚であり、従来自然に生息する生き物ではありません。アメリカザリガニは特定外来生物に指定されています。ビオトープでの飼育はしないようにしましょう。金魚、ザリガニはこどもにとって身近な生き物でもあります。飼育、観察する場合には、ビオトープではなく、専用の水槽や鉢で区別して飼育する事をおすすめします。アメリカザリガニは特定外来生物なので、飼育している生体を近隣の川や池に放流することは違法です。飼育を始めたら、命を終えるまで園内で大切に飼育しましょう。
水場のあるビオトープの管理の方法
基本的に放置で良いですが、水質や植物が安定する環境になるまで時間がかかります。また、天候や日当たりにより急に環境が変わる事があります。また、3~5年に一度は池の全体的な清掃や、ポンプ等の機材のメンテナンスが必要になります。以下に日常のメンテナンス方法をアドバイスします。
●水が白濁している場合
池を作った直後はバクテリア(※)の数が少なく、水質が安定していません。暫く様子をみましょう。

※池底や石や土の表面には多様なバクテリア(細菌)が住みつき、汚れやメダカの糞や死骸等の有機物を分解して水をきれいにする働きをします。バクテリアは「自然の浄水装置」の役割をします。
●水量が減ってきた場合
ビオトープの水は雨が降らない限り、蒸発し減っていきます。水が減っている場合には注水しましょう。ある程度広いビオトープであればカルキ抜き(塩素抜き)の必要はありません。
●藻や水草が増えてきた場合
剪定(カット)、除去しましょう。藻が大量発生し、水質が悪くなった(水が緑色になった場合など)には、オーニング等で水面の日当たりを調整しましょう。日当たりが良すぎて、藻が増える事があります。また、ミナミヌマエビやタニシを入れると藻を食べてくれます。メダカ同様にビオトープ内で繁殖もするので、便利な味方です。
●エサやり
基本的にエサやりは不要です。メダカは雑食なので、水草についたコケや、ボウフラ(蚊の幼虫)を食べます。ただし、こどものあそびの一環で、市販のメダカのエサをあげても良いと思います。餌付けできるので、近づくと寄って来るようになります。
安全面に関して
水場を作ると、こどもが落下する危険性があります。実際に誤って落下するケースもあります。「こどもが入れないようにする事」が一番安全な対策かもしれませんが、それではこどもが自然に触れる経験はできなくなります。園庭にビオトープを作ると、水場だけでなく、虫に刺されたり、毒のある植物があったりと危険な事が沢山あります。こういった危険とこどもの経験とのバランスを考える必要があります。
私たちは、一番大切な事は、園庭をこどもと一緒に使う(遊ぶ)先生の存在だと考えています。先生が危険を認識していれば、見守りの質も向上し、安全は守られます。実際に、水場を作った園の先生からは、「落下するケースはあるが、プールあそびと同じでちゃんと監視しているので、危険だと思う事はありません。落ちたこどもも、それが経験になり自分の身体をコントロールする力がついたり、お友達に危険を知らせる役目を担ってくれる事もあります。」との意見をいただきました。
私たちは、園庭づくりのプロとして、リスクとハザードの研修をおすすめしています。リスクとは、成長のために経験すべき危険(経験を通じて成長につながる危険)であり、ハザードは経験不要な危険(すぐに取り除くべき)です。これを、園内研修として先生方に参加いただき、議論し決めていきます。水場を作る際にも、柵を設けるべき、設けないべき、そもそも危険だから水場自体を作らないべき、様々な意見が出ます。それらの意見と、自園で育みたいこどもの姿を重ね合わせて、その園ならではの結論を導き出します。研修内での意見交換を通じて、自園の保育理念の再確認の場にもなり、園庭だけでなく、他の環境の見直しのきっかけになり、結果として園全体の保育の質が向上します。
私たちASOBIOについて
私たちは、全国のこども園、幼稚園、保育所の園庭にビオトープを作りのお手伝いをしてきました。ASOBIOは「あそび」と「ビオトープ」を組み合わせた言葉です。詳しい資料のご請求や、ASOBIOがある園の見学、あるいは具体的な園庭づくりのご相談は、お気軽にお問い合わせください。皆様と共に、子どもたちの未来を育む「いのちまんなか」の園庭を創造できることを楽しみにしています。